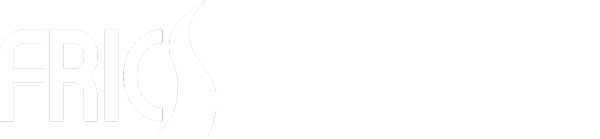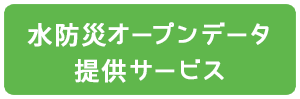レーダ雨量データのデータベース化
レーダ雨量データは、水文観測業務規定 <H29.3改定> において正式な雨量観測データとして位置づけられています。他の水文データと同様、観測データを保存・蓄積することにより、幅広い分野での活用に資することが期待されます。
国土交通省では、レーダ雨量データの有効な利活用に資するため、「レーダ雨量データベースシステム」の整備が一部の地整で進められています。
現行の水文観測業務規程で永久保存が義務付けられているレーダデータは以下となっています。
(1)Cバンドレーダ同時刻合成雨量
(2)XバンドMPレーダ合成雨量
(3)CバンドMPレーダ・XバンドMPレーダ合成雨量
(4)CバンドMPレーダRawデータ
(5)XバンドMPレーダRawデータ
レーダ雨量計観測データはデータ量が膨大であることから、データの利用頻度や活用目的を踏まえたデータベース化の推進が望まれます。
【データベース化が望まれる過去の著名豪雨時のXRAIN画像例】
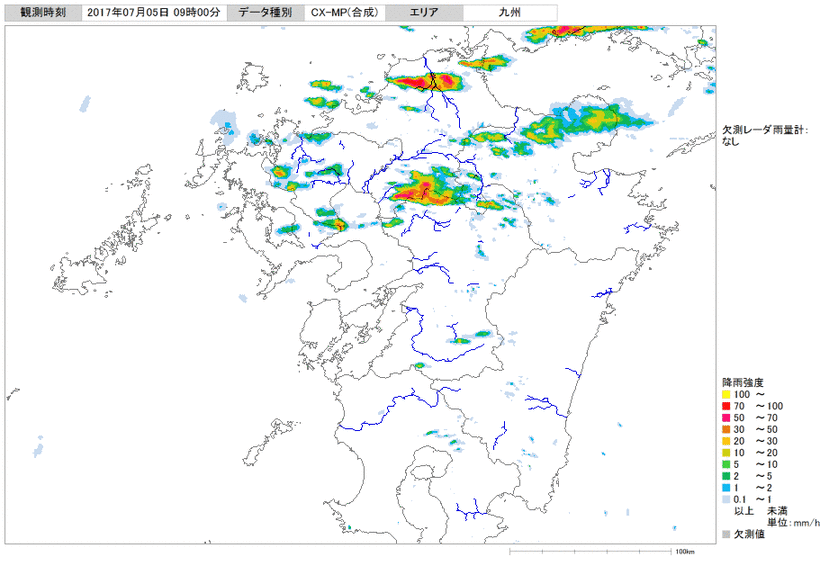
【図1(1)】2017年7月 九州北部豪雨
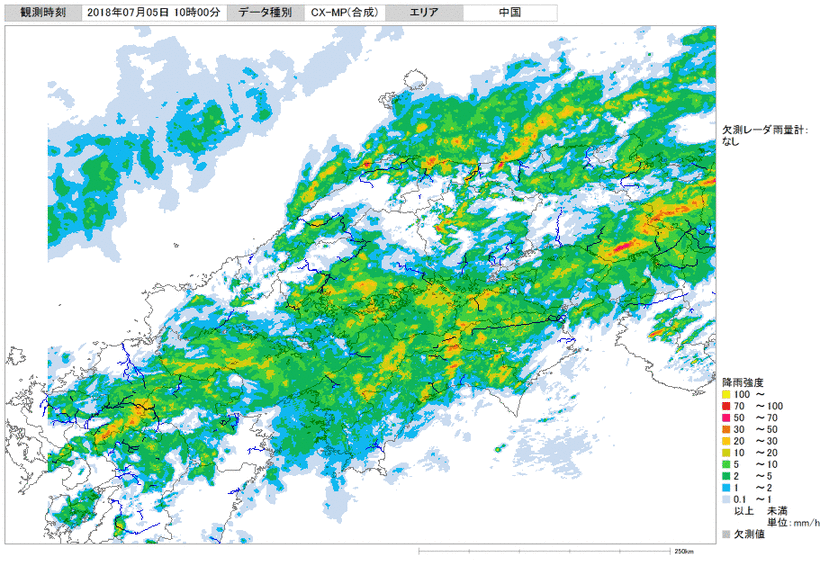
【図1(2)】2018年7月 西日本豪雨
データ統合・解析システム(DIAS:Data Integration and Analysis System)は、地球環境ビッグデータ(観測情報・予測情報等)を蓄積・統合解析し、気象変動等の地球規模課題の解決に資する情報システムとして、2006年度にスタートしました。
XRAINに関する各種データもリアルタイムで収集・蓄積されており、DIASアカウントを取得することにより、研究及び教育目的等で下記のデータの利用が可能になっています。
(1)XバンドMPレーダ合成雨量データ
(2)XバンドMPレーダのRaw・一次処理データ
(3)CバンドMPレーダ・XバンドMPレーダ合成雨量データ
(4)Cバンドレーダオンライン合成雨量データ
レーダ雨量データは時間分解能が1分(または5分)と高く、全国を高い空間分解能(250mまたは1km)でカバーしていることから、データ量が膨大となります。そのため通常は、コンピュータが直接理解でき、データ圧縮時に圧縮率が高いバイナリというデータ形式で格納されます。
バイナリ形式のデータはテキスト形式のデータと違ってパソコンでデータを開いて人間が見てすぐに理解できる形式ではありません。格納している数値を人が目で確認するにはデータ毎に規定されたデータフォーマット(grib2やnetcdf、XRAINデータフォーマット仕様書等、Cバンドレーダ雨量データフォーマット仕様書等)に従ってプログラム等でデータを読み出す(もしくは変換する)必要があります。